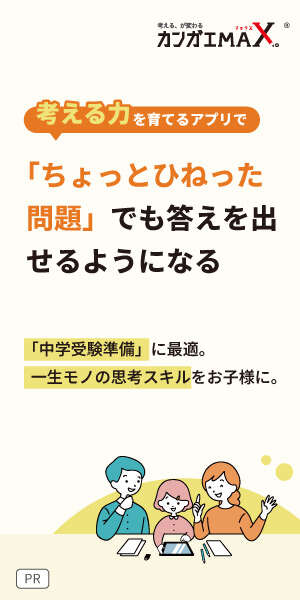カルシウムが豊富「あゆ」の栄養とおすすめレシピ♪

あゆはカルシウムを豊富に含んでおり骨がやわらかいので、骨ごと食べられる調理や、小さなあゆを骨ごと食べることをおすすめします。内臓にはカルシウムの吸収を高めるビタミンDや、ビタミンA、ビタミンB群が豊富なため、内臓も一緒に食べるのがよいとされています。特に多く含まれるビタミンB12は悪性貧血に効果的です。身にはDHA、EPA、ビタミンE、リン、亜鉛が含まれており、骨軟化症、高血圧症状、ストレス、味覚障害などの予防と改善にもおすすめです。

焼きあゆとなすの煮物
なすにはからだを冷やす作用があり、のぼせやすかったり、暑さに弱い人はにはぜひおすすめです。あゆの高血圧症予防の効果に加えて、なすの「コリン」という成分にも血圧を下げたり、胃液の分泌を促したり、肝臓の働きをよくするなどの働きがあります。また、血管を強くするので毛細血管からの出血防止の効果もあり、 旬の夏に食べることでより高い効果が得られます。
あゆの種類と旬
あゆの旬は6月から10月。からだが大きくなり成熟し始めた頃の「成熟あゆ」から、産卵前の「子持ちあゆ」、産卵後の「落ちあゆ」と、様々に楽しめます。成魚の頃は川で過ごし川で秋に産卵します。冬に孵化(ふか)するとすぐに川を下って仔稚魚期には海で過ごし、春になると川を上ります。この頃は既に、すいかやきゅうりのような香りがしますので、川は上るあゆのにおいが漂ってきます。産卵期を迎える秋に産卵後、その生涯を閉じます。一年で死んでしまうので「年魚」とも呼ばれ、産卵後のあゆは栄養も抜けてしまいやせるので「落ちあゆ」「さびあゆ」と呼ばれ ます。
養殖のあゆ
養殖もののあゆは、からだが青っぽい色をしており、えさをたくさん摂取しているため、含有される脂肪分も多くなっています。うろこが日に焼けて少し黒ずんでおり、天然と比べると香りも少し薄いのが特徴です。しかし、現在の養殖は進んでおり、えさは藻を使用した天然に近い飼料を使用しているため、天然ものに近い状態で流通しています。
天然のあゆ
体は黄色みを帯びており、ひれが大きくあごが角ばって大きいのが特徴です。渓流で泳ぐため、ひれが大きくなっており、特に背びれは胴体の幅よりも長く尾びれも大きくなっています。一般に、天然もののあゆの方が身肉に含有される遊離アミノ酸やアンセリン、ペプチドといった成分が多く、養殖ものよりも美味とされています。天然もののあゆは藻などをえさにしているため、すいかに似た香りが特に強く、また、川によって香りや顔つきも異なるため、毎年各地で「利き鮎大会」なるものが開催され、あゆ愛好家の楽しみにもなっています。

背ごしあゆのごま和え
あゆを骨ごとと食べる料理なので、カルシウムが豊富にとれ、その吸収を高めるビタミンDも含まれるので骨粗しょう症予防に効果があります。ごまにはDHAやEPAと同様に働く抗酸化物質が豊富なため、疲労回復効果があり、夏バテの方などにもおすすめです。
あゆをスーパーで選ぶポイント
全体的に黄褐色を帯びているもの、腹部に張りがあり、かたいもの、ぬめりがしっかり付いていてつやがあるものが鮮度がよいものです。頭の付け根、肩に当たる部分が盛り上がっているものはよく太っていて、肉質もよくなっています。
あゆを美味しく味わうための下処理や調理法、保存法
鮮度が落ちやすく、悪くなるとおなかが割れてしまいます。あゆはしっかり冷やしておくとで、ある程度劣化を防ぐことができるので、購入後に持ち帰る場合でも、氷をしっかり入れて冷えたまま持ち帰ること、冷蔵庫で保存するよりかはチルド室で保冷することが大切です。それでも1日2日で食べてください。下処理としてはぬめりを取ってから調理します。このぬめりは、取ってから保存しておくとまた出てきます。調理の直前に洗ってタオルでふくようにして取りましょう。うろこが付いていますので、丸焼き以外はうろこを取ることをおすすめします。

日本料理教室講師田村 佳子
栄養士/調理師/和憩カルチャースペース主催
大学で海洋水産資源の研究後、大手小売業水産担当として勤務。水産の流通を把握してから栄養士を所得。調理師専門学校の日本料理で勤務し、日本料理の技術と知識を習得した後、独立。2008年和憩カルチャースペースを開設し、得意の魚メインにした日本料理教室を開講している。朝日放送「おはよう朝日です」出演、市場や企業とのタイアップレッスン、行政施設などでの教室開講など活動中。