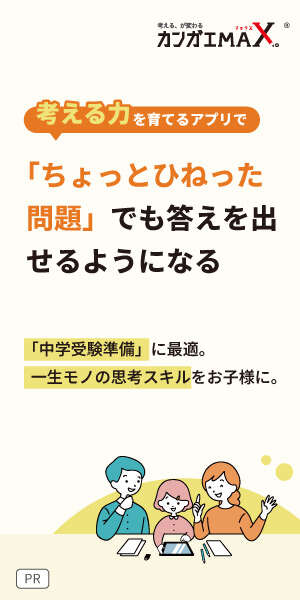ビタミンも豊富「さけ(鮭)」の栄養とおすすめレシピ♪

鮭には、良質なたんぱく質をはじめ、動脈硬化など生活習慣病を予防するEPAや脳の活性化に役立つDHAが豊富に含まれているほか、カルシウムの吸収を助けるビタミンDや血流をよくするビタミンEなど、ビタミンも豊富に含まれています。バランスよく含まれているビタミン類により、貧血、風邪、皮膚疾患の改善と予防、抗ストレス作用や味覚改善作用などの効果が期待できます。また、鮭の赤い身はアスタキサンチンという色素によるもので、抗酸化作用も期待できます。メスよりオスのほうが美味しいとされており、卵に栄養がとられない分、オスの肉には栄養も豊富です。

フライパンで鮭のちゃんちゃん焼き
野菜をたっぷり食べられるちゃんちゃん焼きは、鮭の栄養効果、骨粗しょう症予防や動脈硬化など生活習慣病予防を高めるバランスの取れた料理です。赤い色の元になっているアスタキサンチンは抗酸化作用が強く、さらにこれらの効果を高めます。
さけの身が赤いのは?
鮭はもともと白身の魚ですが、海に出てオキアミなどのえさを食べることで赤い色素が蓄積し、身がオレンジ色に染まります。赤い色素成分はアスタキサンチンと呼ばれるもので、抗酸化力が極めて高く、ビタミンEの約550~1000倍にも相当すると言われ、老化の引き金となる活性酸素から体を守り、血液をサラサラにして、動脈硬化の抑制に期待できると言われています。鮭は川に遡上(そじょう)するとき、強烈な紫外線を浴びるため、活性酸素が大量に発生しますが、強力な抗酸化力を持つアスタキサンチンが活性酸素を除去して、鮭の身を守ってくれています。アスタキサンチンは、糖尿病腎症の抑制、眼精疲労の改善、免疫機能向上、ストレス解消などにも役立つ栄養成分です。

鮭のしっとり柚庵焼き
鮭にはビタミンEやB群、抗酸化作用の高いアスタキサンチンが多く含まれているため、風邪、皮膚疾患の改善と予防、抗ストレス作用の効果が期待できます。ゆずを皮ごと使うことで、皮の方が栄養価が高くビタミンCは果汁の4倍近く含まれています。ビタミンCには風邪の予防や疲労の回復、肌荒れなどに効果が期待でき、鮭の効果をより引き立ててくれます。
鮭の種類と旬
日本で食べられる国産天然の生鮭(塩鮭ではないもの)は一般的にシロザケのことを言います。「あきざけ」「あきあじ」「ぎんけ」「ときしらず」「けいじ」など色々な呼び方がありますが、鮭の種類は以下のとおりになります。また、「さけ」と「ます」の違いがよく問われますが、厳密な違い、分け方が無いのが現状です。
シロサケ
- 別名:秋鮭(あきざけ)・秋味(あきあじ)
北大西洋を回遊し、秋から冬にかけて産卵のために沿岸に近づく鮭。成熟して脂が少なくさっぱりしており、主な産地は北海道、青森、秋田です。
- 別名:銀毛(ぎんけ)
産卵のために沿岸に近づく鮭の中でも、未成熟のため脂がのり、銀色のうろこがきれいに生えそろっている鮭。主な産地は北海道で高価に流通しています。
- 別名:時不知(ときしらず)・時鮭
産卵のための回遊をせずに、日本近海に残り、初夏に沖で取られる未成熟な鮭。脂がよくのっており、希少価値があり北海道が産地です。
- 別名:目近
秋に日本海側の河川にのぼる途中、オホーツク海沖でとれた鮭。成熟が進んでいないため脂がのっており、高価に販売されています。
- 別名:鮭児(けいじ)
夏から秋に接岸した鮭の中に混ざっている若いが体が大人なみに大きい鮭。本来は翌年に産卵する個体であるため、未成熟で脂があり卵や白子ができない分、身が濃厚な味わいになります。1万匹に1から2匹とも言われ、幻の魚として1kg当たり数万円にもなります。
ベニサケ(別名:ベニ)
身の色がサケ科の中でもっとも赤い鮭。他の鮭と違い、ふ化後に淡水域で1~2年を過ごし、産地はアメリカ、ロシア、カナダ、アラスカなどです。
ギンサケ(別名:ギン)
紅鮭やキングサーモンに次いで身が赤い鮭。最近は養殖もののチリ産が大量に輸入されており、北太平洋の北部に分布しています。
カラフトマス(別名:ピンクサーモン)
鮭の仲間の中で多く獲られる鮭。身がやわらかく、味が他の鮭よりも劣るため、缶詰めの原料になっています。卵巣は塩蔵されて、すじこ、いくらにされています。北大西洋から日本海まで幅広く分布しています。
マスノスケ(別名:キングサーモン)
アメリカでもっともおいしいと言われ、すしネタとしても高級な鮭。太平用の東北以北、日本海、オホーツク海、ベーリング海に生息し、国内には少なく、体長2m、重さ60kgにもなり、養殖もされています。脂が一番乗っているのが特徴です。
サクラマス(サクラマス・ヤマメ)
一生、河川で過ごすものがヤマメで、海に下るものがサクラマスと呼ばれます。北海道から九州まで広く分布しており、北へ行くほど海に下り、秋の産卵に備え、桜の咲くころに遡上(そじょう)をはじめます。脂がのっているのにさっぱりしています。
ニジマス(ニジマス・トラウトサーモン)
ニジマスを品種改良した新品種をトラウトサーモンと言います。ほどよくのった脂が人気で、定番のすしネタにもなっておりノルウェー、カナダ、チリからの輸入量が急増しています。
タイセイヨウサケ(アトランティックサーモン)
生食用の鮭。寄生虫の心配のない人工飼料と徹底管理された養殖環境で育てられており、脂がのり甘味があります。多くはノルウェー産です。

鮭とかぶらの酒粕甘煮
かぶらの根はビタミンCを多く含み、でんぷん消化酵素のアミラーゼを含んでいます。胸焼けや食べ過ぎの不快感を取って整腸作用が期待できます。葉も使うことでカロチン、ビタミンC、鉄、カルシウム、カリウム、食物繊維なども摂取でき、鮭の栄養効果も含め、バランスの取れた胃腸の弱っているときにお勧めの食事です。
鮭をスーパーで選ぶポイント
身が割れておらず、張りがあってつやがある切り身を選びましょう。身の赤色が濃いほうがより沢山のえさを食べ、栄養を豊富に蓄えているので色の濃いものを選ぶと味わい深い切り身を食べることができます。
鮭を美味しく味わうための下処理や調理法、保存法
理想的な保存方法
軽く塩を振って15分以上置いてから水気をふき取り、一つずつキッチンペーパーで包み、ラップをして冷蔵庫煮保存してください。冷凍も同様です。
理想的な保存期間の目安(賞味期限)
冷蔵庫で2~3日程度、冷凍庫なら1ヶ月が目安です。
香ばしい香りがつく料理
焼き物、揚げ物は焦げ目の香りで魚の臭みが取れますので塩をしてふくだけで下処理終了です。加熱しすぎるとパサつき、味も落ちるので注意してください。
香ばしい香りがつかない料理
蒸し物、煮物、汁物は煮汁に臭みがにじみ出たり、蒸し物ではにおいがこもったりしてしまいます。塩をした後さらに臭みをとる、霜降りの作業までが下処理になります。

日本料理教室講師田村 佳子
栄養士/調理師/和憩カルチャースペース主催
大学で海洋水産資源の研究後、大手小売業水産担当として勤務。水産の流通を把握してから栄養士を所得。調理師専門学校の日本料理で勤務し、日本料理の技術と知識を習得した後、独立。2008年和憩カルチャースペースを開設し、得意の魚メインにした日本料理教室を開講している。朝日放送「おはよう朝日です」出演、市場や企業とのタイアップレッスン、行政施設などでの教室開講など活動中。