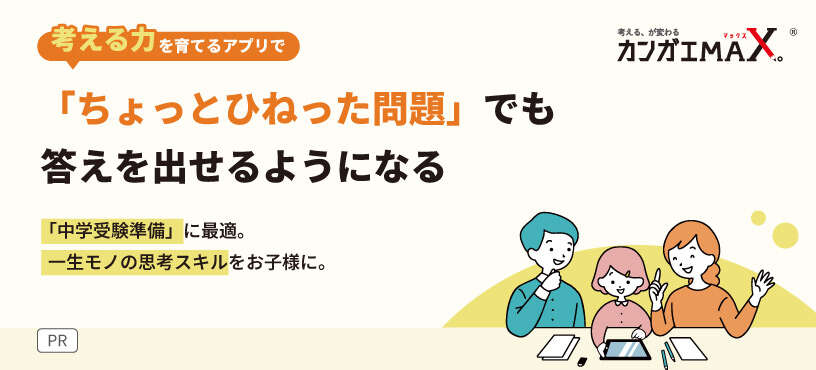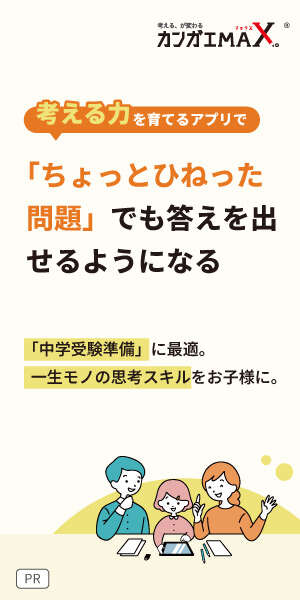レシピ(管理栄養士監修)
毎日おすすめレシピ

はもフライの梅肉らっきょうタルタル添え
コレステロール低下作用、血栓抑制作用があり、高血圧や動脈硬化の予防にも有用なDHAやEPA等がたくさん含まれるはもをフライにすることで、同じ揚げものでも生活習慣病へのリスクを軽減することができます。カルシウムも豊富に摂取でき、コンドロイチン硫酸の働きで美肌にも効果が得られます。梅肉とらっきょうの入ったタルタルソースを添えることで、梅が胃腸を調え、らっきょうの硫化アリルが、ビタミンB1の吸収を通常の7倍にも高め、血液を浄化、血行をよくし、血をサラサラにしてくれます。
美肌
更年期・ホルモンバランス
連載・特集
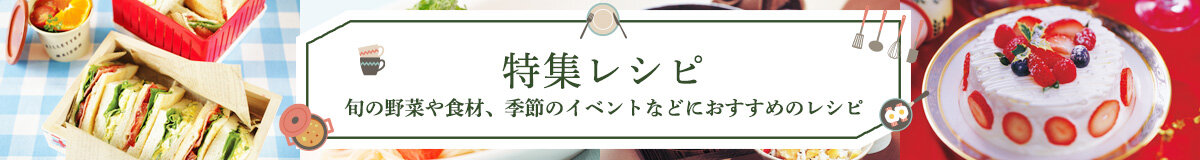
特集レシピ
旬の野菜や食材、季節のイベントなどにおすすめのレシピです。

旬のお魚レシピ
ヘルシーで栄養たっぷりな旬のお魚の選び方とアレンジレシピ。

女性のお悩み解決献立レシピ
管理栄養士が女性の悩みに応えるバランス栄養献立レシピ。

筋力・持久力・瞬発力UP!献立レシピ
筋力UP、持久力UP、瞬発力UPのための栄養を考えた夕食献立レシピ。
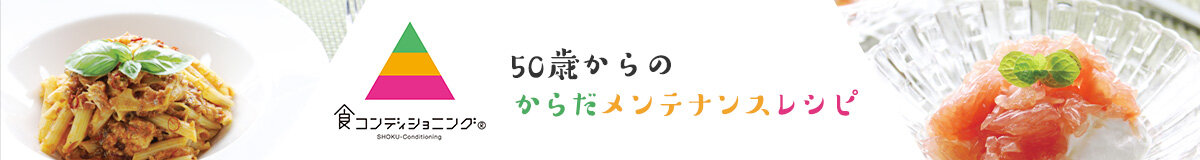
食コンディショニング 50歳からのからだメンテナンスレシピ
からだメンテナンスのポイントとかんたんヘルシー料理の組み合わせでストレスフリーに健康管理のコツを解説。
>食コンディショニングとは

食コンディショニング ダイエット&ヘルスケアレシピ
健康的にキレイを目指す!ダイエット・ヘルスケアの食事のコツ。
>食コンディショニングとは

人気の低カロリーレシピ
年齢を重ねると、ホルモンバランスや運動量の減少によって基礎代謝が低下して痩せにくくなると言われています。定番おかずやスイーツが食材や調理方法を少し変えるだけで低カロリーになる管理栄養士おすすめのレシピをご紹介。バランスよく食べて中年太り対策&健康的なダイエットを。
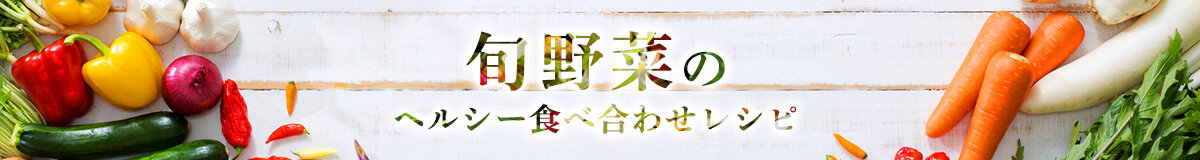
旬野菜のヘルシー食べ合わせレシピ
美容と健康に効果的な栄養たっぷり!旬野菜の食べ合わせレシピ